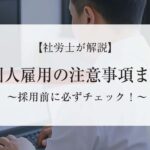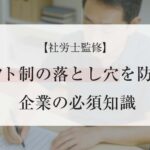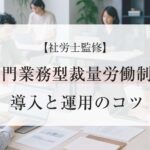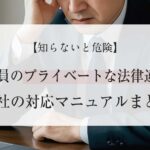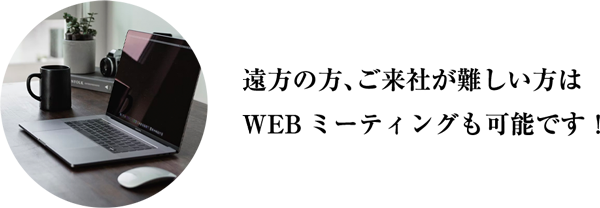【超重要!】テレワーク時代の必須対応:労務管理とトラブル予防のポイント
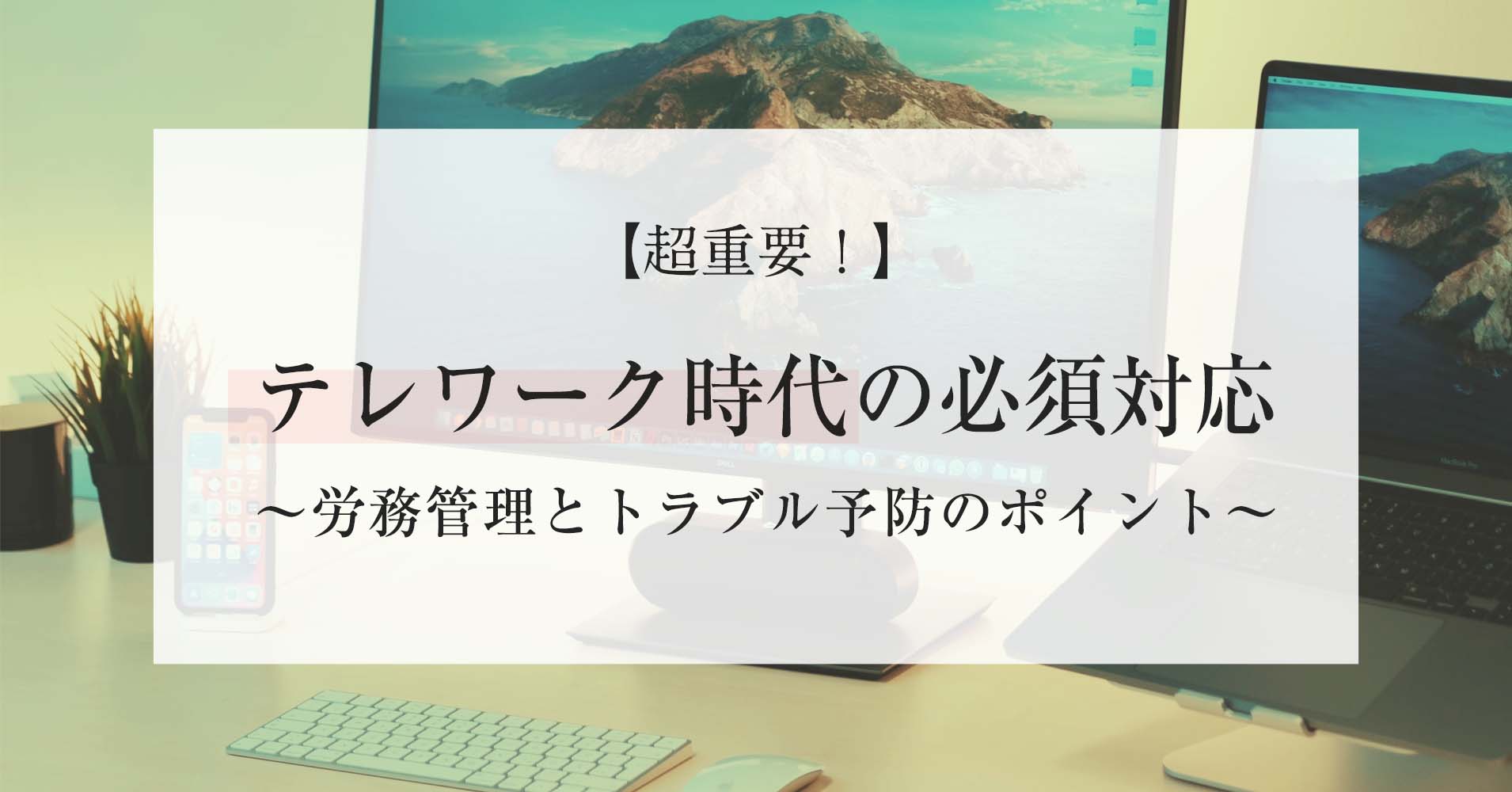
新型コロナウイルス感染症のパンデミックを契機に急速に普及したテレワークですが、感染状況の落ち着きに伴い、その運用を見直す企業も増えています。
一方で、テレワークを継続・拡大する企業にとっては、オフィス勤務とは異なる環境での「労働時間管理」や「労使間のコミュニケーション」といった課題が改めて浮き彫りになっています。
特に、「テレワークでは勤怠管理が難しく、生産性向上にもつながらない」といった企業の考え方や、「管理職の目が届かないと、仕事をさぼる従業員がいるかもしれず、チェック・指導もできないから不安」といった声は少なくありません。
また、テレワーク中の従業員側からも、「仕事をさぼっていると思われていないか」「評価が下がるのではないか」といった不安があるといいます。
このようなテレワーク特有の課題に対し、企業はどのように対応すれば良いのでしょうか?
今回は、テレワークを適切に運用するための労働時間管理の方法と、労使トラブルを未然に防ぐためのポイントについて解説します。
この記事の目次
テレワーク時の労働時間管理の基本
労働時間管理の基本は「開始・終了の報告」と「業務中の在席把握」
テレワーク(在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務)は、従業員が通常の勤務と異なる環境で就業することになります。そのため、労働時間の管理方法について確認し、あらかじめルールを決めておくことが必要です。
労働時間の管理には、主に以下の二つの観点があります。
1.始業・終業時刻の管理
従業員の始業・終業時刻を管理するため、報告や記録の方法をあらかじめ決めておきます。
具体的な報告方法としては、Eメール、電話、勤怠管理ツールなどがあります。
厚生労働省のアンケート調査によると、テレワークの労働者が事業場外みなし労働時間制の対象となっている場合でも、「勤務管理システムに自己申告で入力」が最も多く(40.1%)、次いで「上司にメール等で報告」(27.1%)となっています。
始業・終業時刻を変更する場合や、所定労働時間中に業務を中断する場合(中抜け時間)についても、あらかじめ運用ルールを決めておくことが重要です。
2.業務時間中の在席確認
在席・離席が確認されることによって、管理者の不安や、テレワーク利用者の不安を軽減できます。
始業・終業時刻の確認に加えて、労働時間中に適正に業務が行われているか管理が必要な場合もあります。
在席確認の方法としては、Eメールや労務管理ツールによって在席・離席状況を確認する、労働時間中は常に電話連絡ができる状態とする、テレワークのパソコン作業の画面を閲覧できる、といった例があります。
ただし、目標管理制度が適切に運用されている場合や、業務内容によっては在席管理が適合しない場合もあることに留意が必要です。
「中抜け時間」の取り扱い
テレワーク中に業務を中断する「中抜け時間」は、特に育児や介護を行っているテレワーク利用者にとっては発生する可能性があります。
このような場合について、労働時間管理や情報に関するルール化が求められます。
労働基準法上、使用者は中抜け時間を把握することとしても、把握せずに始業および終業の時刻のみを把握することとしても、いずれでもよいとされています。
中抜け時間を把握する場合、例えば1日の終業時に労働者から報告させることが考えられます。
中抜け時間の取り扱い
中抜け時間の取り扱いとしては、以下の例が考えられます。
•中抜け時間を把握する場合
休憩時間として取り扱い終業時刻を繰り下げる、または時間単位の年次有給休暇として取り扱う。
•中抜け時間を把握しない場合
始業および終業の時刻の間の時間について、休憩時間を除き労働時間として取り扱う。
これらの取り扱いについては、あらかじめ使用者が就業規則等において定めておくことが重要です。
アンケート調査では、「中抜け時間の有無にかかわらず1日の労働時間分勤務したものと取り扱っている」が最も多く(36.4%)、次いで「賃金から差し引かれるまたは中抜け分だけ労働時間を延長している」(25.3%)となっています。
労務管理ツールの活用
テレワークによる労働時間を適切に把握するためには、労務管理ツールを活用できます。
労務管理ツールとは、勤怠管理(労働時間の管理)や業務管理(業務遂行状況の把握)などを適切に行うために用いるツールです。
ツールの特徴や効果を確認したうえで、従業員と上司が互いに安心して利用できるツールを活用することが推奨されています。
労務管理ツールの活用例としては、スケジュール管理ツール(従業員の業務管理やスケジュールの共有)や、プレゼンス管理ツール(従業員の在席確認や業務状況の把握)があります。
また、情報共有ツールも活用できます。
勤怠管理ソフトを利用すれば労働時間の集計が自動的にできるため、時間外労働規制への対応を自動化できるメリットがある一方、利用料が必要となる、従業員の打刻忘れや利用慣れへの対応が必要といったデメリットもあります。
テレワークに関する労使トラブル事例から学ぶ
テレワークの導入は、新たな労使トラブルを招く可能性もあります。ここでは、いくつかの裁判例から学ぶべき点を見ていきましょう。
事例1:在宅勤務の勤怠ルール違反
在宅勤務でもルール違反は懲戒有効
在宅勤務時の勤怠ルール違反事案 東京地判令和5年4月26日の事例では、会社が定めた在宅勤務の勤怠ルール(勤務開始・終了時のメール連絡と業務報告、会社指定URLでの打刻)に営業課長が約1年2カ月間違反し、虚偽申告や調査非協力があったとして懲戒処分の有効性が争われました。
裁判所は、ルール違反の重大性などを考慮し、降格処分を有効と判断しました。
この事例は、テレワークに関する適切なルール設定と、それを徹底するための厳格な勤怠管理の重要性を示しています。
しかし、企業にとっては、そこまでのコストと労力をかけてまで在宅勤務を続けるメリットがあるのか、という点も考慮すべき問題となります。
事例2:在宅勤務中の手待ち時間
手待ち時間も労働時間、減額不可
在宅勤務時の「手待ち時間」に関する事案 東京地判令和5年4月27日の事例では、在宅勤務中にパソコンを操作していない時間が労働時間に当たるかどうかが争われました。
会社はPCの作業ログを根拠に、パソコン作業が確認できない時間分の給与返還を求めましたが、裁判所は、仕事量が少ない時期の作業していない時間はいわゆる手待ち時間であると判断し、会社の請求を認めませんでした。
この事例は、「在宅勤務の社員が本当に仕事をしているのかわからない」という社内の不安が背景にあったことを示唆しています。
作業の合間に「手待ち時間」が生じるのは事務所勤務でも同じであり、この時間は労働時間に含まれるため、まずは仕事量を適切に振ることを検討すべきです。
柔軟な働き方を導入するには、従業員への信頼が前提となります。
もし従業員を信頼できないのであれば、在宅勤務を廃止・縮小する方が現実的かもしれません。
事例3:テレワーク職員への出社命令・賃金カット
在宅前提なら出社強制はNG
テレワーク職員に対する出社命令と賃金カット事案(アイ・ディ・エイチ事件) 東京地判令和4年11月16日の事例では、労働契約書上の就業場所は本社事務所と記載されていたにもかかわらず、実際の勤務実態や代表者の発言から、「就業場所は原則として自宅で、業務上の必要がある場合に限って本社事務所への出勤を求めることができる」契約と解釈されました。
感情的なやり取りを背景とした出社命令は、業務上の必要性が認められないと判断され、それに応じなかったことによる不就労は会社に帰責事由があるとして、会社は従業員に賃金を支払う義務があるとされました。
他方で、従業員からの残業代請求は、使用者による指揮監督がない在宅勤務であり、始業・終業時刻が一定せず、従業員が就業時間について一定の裁量を持っていたと認められること、パソコン操作ログからも労働時間に疑義が生じるとして、請求が棄却されました。
また、会社からの不就労分の賃金返還請求も、過去に不就労時間を問題にすることなく賃金を支払ってきたことから、賃金控除を放棄していたとみるべきとして棄却されています。
この事例は、テレワークにおける労働時間把握(管理)の難しさや、職場のコミュニケーション形成の困難性が浮き彫りになったケースと言えます。導入されていた時間管理ツールも、双方にとって不十分と判断されました。
適切なテレワーク運用に不可欠な5つの視点
これらの事例からもわかるように、テレワークを適切に運用するためには、以下の点に留意が必要です。
1.ルール不明瞭はNG!まず線引きをはっきりと
就業規則やテレワーク規程などで、対象業務、対象者、労働時間、賃金(手当・交通費等)、費用負担、中抜け時間、服務規律などを明確に定めることが不可欠です。特に、どのような場合にオフィスへの出社を求めることがあるのかなど、誤解を生まずに明確に定めておく必要があります。
2.勤怠・業務は「見える化」でスッキリ管理
始業・終業時刻の報告・記録方法、中抜け時間の取り扱い方法、業務時間中の在席確認方法などを具体的に定め、従業員に周知します。
労務管理ツールを効果的に活用することも有効です。単に労働時間を管理するだけでなく、日報や週報、目標設定など、業務管理の方法を工夫することも重要です。
3.顔を合わせない分、意識的な会話を大切に
テレワークではコミュニケーション不足に陥りやすいため、定例会議や共通出勤日を設定したり、WEB会議や電話活用を奨励したりするなど、意識的に情報や認識を共有する機会を設けることが望ましいです。
テレワークの健全で効率的な運用のためには、ガイドラインを参考に、使用者による現認ができない状況でも労働時間管理を工夫する必要があります。
4.信頼なくしてテレワークなし、公平評価が必須
テレワークを円滑に進めるためには、従業員への信頼が前提となります。
また、テレワーク業務における業績評価に不安を抱かせないように、公正な評価方法を構築することが望ましいでしょう。
5.ルール見直しは慎重に。思わぬリスクに備えよう
テレワークに関する規定の廃止・縮小を検討する際には、就業規則の不利益変更や、労使慣行、勤務地限定合意、権利濫用といった複雑な法的論点が存在します。
安易な廃止・縮小はトラブルの原因となり得ます。
安心してテレワークを続けるために、私たちにご相談ください
テレワークは、事業継続性の確保やワーク・ライフ・バランスの実現、優秀な人材の確保、生産性の向上など、多くのメリットがあります。
その一方で、適切な労働時間管理や労使間のコミュニケーション、労務管理上の課題も抱えています。
特に労働時間管理では、勤怠管理ツールや業務管理ツールの活用、始業・終業時刻の報告や記録、中抜け時間のルールを明確にするなど、オフィス勤務とは違った工夫が必要です。
また、テレワークでの労使トラブルを防ぐためには、ルールの明確化と周知、管理者と従業員の十分なコミュニケーションが欠かせません。
テレワークを導入・運用・見直しする際は、自社の状況をよく分析し、従業員とも十分に協議しながら進めることが重要です。
ただ、テレワークには就業規則の整備や勤怠管理方法の見直し、評価制度の構築などが伴います。
テレワーク規程の廃止・縮小を検討する際も、複雑な法的リスクがあります。
これらを誤ると、大きなトラブルや訴訟に発展しかねません。
だからこそ、実務と法的リスクに精通した社会保険労務士に相談し、専門家の視点から最適な形を設計することが大切です。
テレワークを単なる制度に終わらせず、企業の成長にしっかり結びつけるためにも、ぜひ当社にご相談ください。
豊富な経験をもとに、御社に合わせた具体的で実践的なサポートをご提供いたします。
こんな記事も読まれています
プロフィール

神奈川県平塚市
社会保険労務士法人・行政書士法人
アーチス
労務に関わる手続き・問題から助成金まで、幅広くお問い合わせに対応していますのでどうぞ安心してご相談ください。
関東エリアを中心に遠方のお客様はZOOMミーティングにより全国どこからでもリモートでのご対応が可能。
20人以上の専門性を持ったスタッフが対応を手厚く、よりスピーディーに行います。