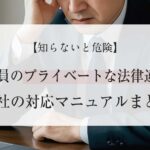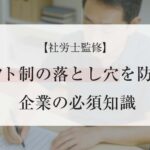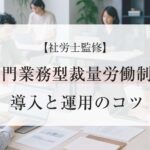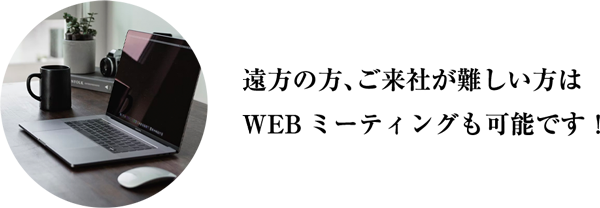【保存版】労災発生時の初動対応とNG行動まとめ
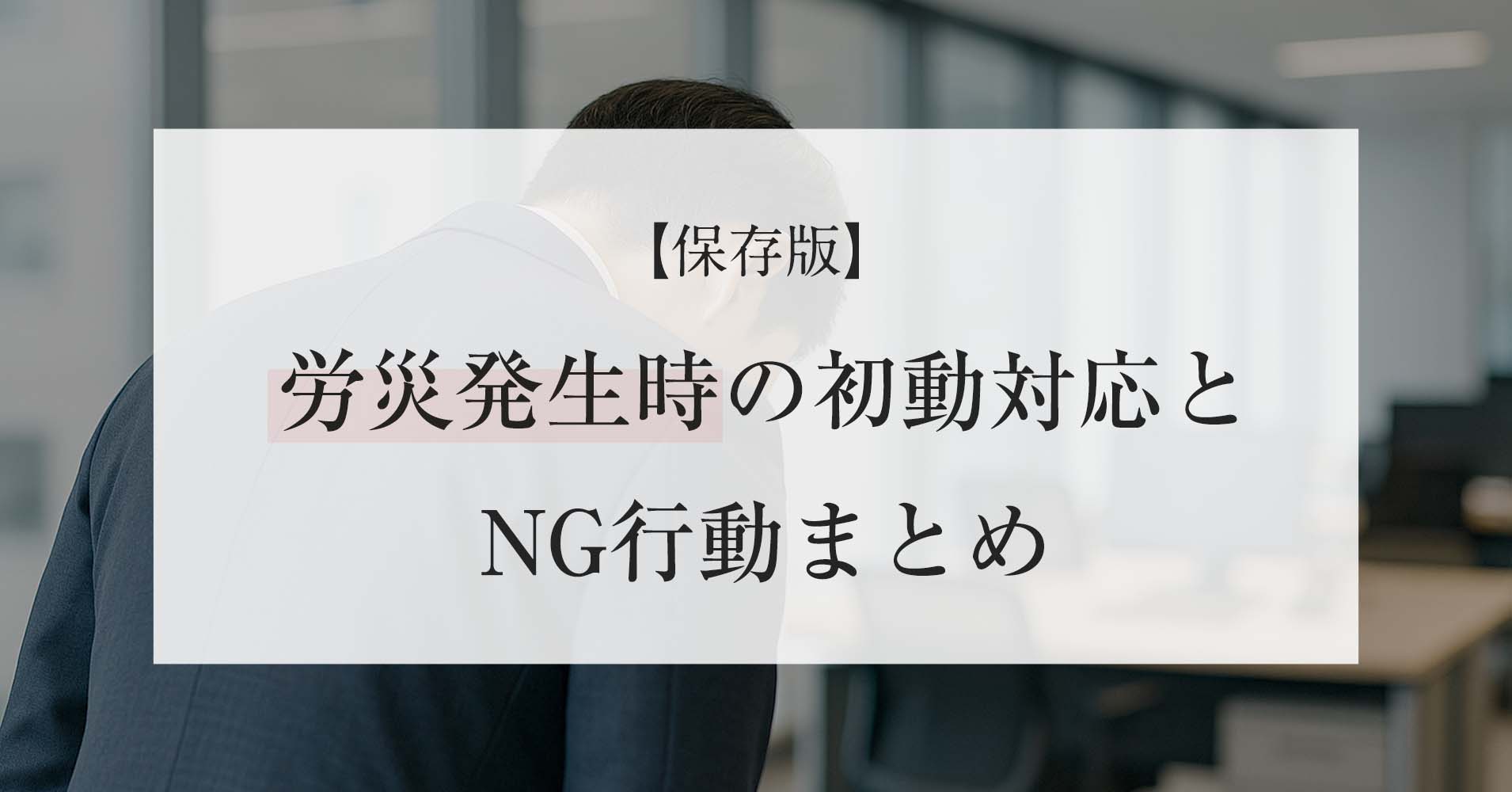
労災事故は、どの企業にも起こり得ます。
そして対応を一歩誤れば、高額な損害賠償請求、長期の訴訟、企業の信用失墜に直結します。
実際、「よかれと思って」の安易な謝罪や労災認定、家族への不用意な情報提供が、数千万円単位の賠償や炎上トラブルに発展した例も少なくありません。
この記事の目次
会社が守るべき原則
労災事故発生時に会社が守るべき原則はシンプルです。
1.事実に基づく冷静な対応
2.窓口の一本化と正確な記録
3.法的根拠に基づく説明と毅然とした対応
4.安易な「便宜」や感情的対応の禁止
5.安全配慮義務・メンタルヘルス対策の徹底
これらを軽視すると、企業にとって大きなリスクとなります。
この記事では、紛争を未然に防ぎ、会社が「絶対にやってはいけないこと」と「賢い対応策」を具体的に解説します。
初期対応の基本:冷静な事実確認と窓口の一本化
労災事故発生後は、感情的にならず、冷静な事実確認を徹底しましょう。
会社がすべきこと
•従業員の緊急連絡先を確認し、不明な場合は本人に確認します。
•面談時は担当者を決め、必ず複数人(対応者と記録者)で対応し、やり取りを正確に記録すること。これは「言った言わない」のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。
•事故発生や従業員の被災、家族へのご心配に対し、「ご心配をおかけして申し訳ありません」とお詫びすること自体は問題ありません。
•窓口は本社などの専門部署に一本化し、現場担当者には安易な対応をさせず、専門窓口へ誘導するよう徹底します。
会社が注意すること
•家族と称する人物の身元や、従業員の正式な代理権限を慎重に確認すること。曖昧なまま対応すると、不要なトラブルを招く恐れがあります。
•お詫びは「会社に事故の原因や責任があることを認めるものではない」と、担当者間で認識を共有し、家族側が責任認定と解釈しようとしたら明確に否定してください。
会社が絶対に行ってはならないこと
•現場の責任者単独で対応すること。労務に関する知識不足や心理的負担から不適切な対応につながりかねません。
•会社内部の情報を安易に家族へ漏らすこと。従業員本人が同席していても、プライバシー保護の観点から慎重に対応すべきです。
「誠意を見せろ」への対応:法的ルールの設定
労災事案では、家族から「誠意を見せろ」といった漠然とした要求が出ることがあります。
これには法的な基準で毅然と対応します。
会社がすべきこと
•会社の対応が、民法の損害賠償義務、労働基準法の災害補償義務、労災保険法などの「法律」に基づいていることを明確に伝えます。
•「業務起因性」と「安全配慮義務違反」が法的判断の鍵となることを説明します。
•法的根拠のない要求には応じられないことを伝えます。
•家族からの要求や質問は、「書面で提出する」よう求めること。これにより、やり取りの正確性が確保できます。
•社内では「上司に確認してからご回答します」という言葉を多用し、安易な個人判断を避ける。決定権は上位職者が持つ「ライン」での対応を徹底します。
会社が絶対に行ってはならないこと
•「誠意」という抽象的な要求に対し、無為に対応を続け、要求をエスカレートさせること。これは際限のない紛争の引き金になりかねません。
•法的根拠を曖昧にしたまま、感情的な要求に引きずられること。
労災認定の判断:「安易な便宜」は破滅を招く
「よかれと思って」という安易な判断が、後々会社を窮地に追い込むケースが少なくありません。
会社がすべきこと
•労災手続きの説明と、会社がその怪我を「業務上のもの(業務起因性あり)」と認めるかは明確に区別するべきです。
•会社として業務起因性を認める場合は、積極的に労災請求を勧め、手続きを支援することで、自社の災害補償義務が軽減されます。
•労災認定の最終判断は労働基準監督署長が行うことを説明し、事実確認が困難な場合は「労働基準監督署の調査・判断に委ねる」という姿勢を示しましょう。
会社が絶対に行ってはならないこと
•事実が不明確であったり、業務起因性の認識がないにもかかわらず、「よかれと思って」安易に労災と認めたり、休業補償給付支給請求書における事業主証明欄に安易に押印したりすること。一度認めた事実は後から覆すのが極めて困難となり、数千万円規模の損害賠償請求に発展する可能性があります。
精神障害と長時間労働:安全配慮義務の落とし穴
労災は身体的な負傷だけでなく、精神障害にも及びます。
特に長時間労働を原因とする精神障害は、会社の安全配慮義務違反を問われる大きなリスクとなります。
会社がすべきこと
•従業員の心身の健康を損なわないよう注意する「安全配慮義務」の一環として、メンタルヘルスケアをする必要があります。
•厚生労働省が推奨する「セルフケア」「ラインケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」の「4つのケア」を継続的・計画的に実施してください。
•特に管理監督者に対し、メンタルヘルスに関する教育・情報提供を徹底し、従業員の異変に早期に気づき対応できる体制を構築しましょう。
•常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生委員会を設置し、メンタルヘルス対策を重要な議題として積極的に審議する義務があります。 ストレスチェック制度の活用も重要です。
会社が注意すること
•長時間労働が精神障害の労災認定に直結する可能性を認識すること。特に、発病直前1ヶ月に約160時間以上、または3週間に約120時間以上の時間外労働があった場合、「極度の長時間労働」として強い心理的負荷と認められます。 これ以下でも、連続した長時間労働や、ノルマ達成の困難さ、転勤など他の業務上の出来事と相まって、強い心理的負荷と判断され得ます。
•私生活上のストレスや個体側要因があっても、業務による強い心理的負荷が認められれば労災認定され得るため、安易に業務外を主張しないことです。
会社が絶対に行ってはならないこと
•メンタルヘルス対策を全く実施しないこと。これは安全配慮義務違反として、高額な損害賠償責任を問われる大きなリスクとなります。
•従業員の労働時間を管理せず、過度な長時間労働を野放しにすること。
後遺障害への対応:労働条件の見直しと対話
重い労災事故で後遺障害が残り、これまでの業務が困難になった場合、会社は長期的な視点での対応が求められます。
会社がすべきこと
•被災者の就労継続意思を確認し、従来の業務が困難であれば、従事し得る他の業務の有無を真摯に検討する必要があります。
•家族も交え、今後の労働条件や配置について十分に話し合いを行うことが重要です。
会社が絶対に行ってはならないこと
・代替業務を検討せずに安易に解雇すること。これは労働契約法16条に抵触し、権利濫用として無効と判断される可能性が高く、法的紛争に発展します。
労災対応は専門家と共に、迅速かつ的確に
労災事故の対応は、単なる事務手続きではありません。
一つの判断ミスが、数千万円規模の損害賠償請求や長期の裁判、企業ブランドの失墜へ直結する可能性があります。
「とりあえず謝っておこう」「よかれと思って労災と認めてしまった」――こうした安易な対応が、最も危険です。
実際に、現在も多くの企業が労災をめぐる紛争対応に追われています。
だからこそ重要なのは、初期対応の一手を誤らないこと。
そのためには、法的知識と労務管理に精通した専門家の関与が不可欠です。
そして、もしすでに紛争が進行していても、諦める必要はありません。
法的知識と労務管理の実務に精通した専門家が入ることで、事態を整理し、出口を見いだせるケースも少なくないのです。
私たちは、労災事故の発生直後からの対応、労基署との折衝、被災者や家族との交渉支援まで、数多くの企業をサポートしてきた実績があります。
「うちの会社もリスクがあるかもしれない」「もう手遅れかもしれない」と感じている方も、まずは一度ご相談ください。
早めの一歩が、会社と従業員を守り、紛争の長期化を防ぐ最大の防御策となります。
こんな記事も読まれています
プロフィール

神奈川県平塚市
社会保険労務士法人・行政書士法人
アーチス
労務に関わる手続き・問題から助成金まで、幅広くお問い合わせに対応していますのでどうぞ安心してご相談ください。
関東エリアを中心に遠方のお客様はZOOMミーティングにより全国どこからでもリモートでのご対応が可能。
20人以上の専門性を持ったスタッフが対応を手厚く、よりスピーディーに行います。