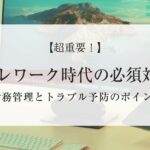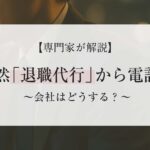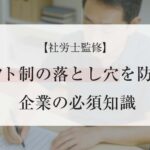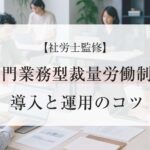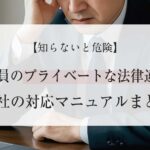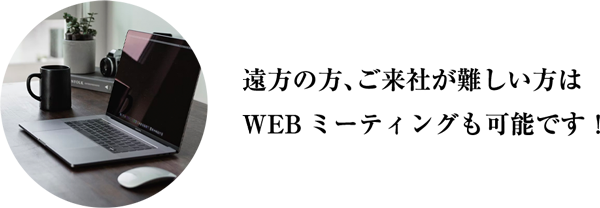初めてのジョブ型雇用 導入ガイド 〜制度設計と実務対応のポイント〜
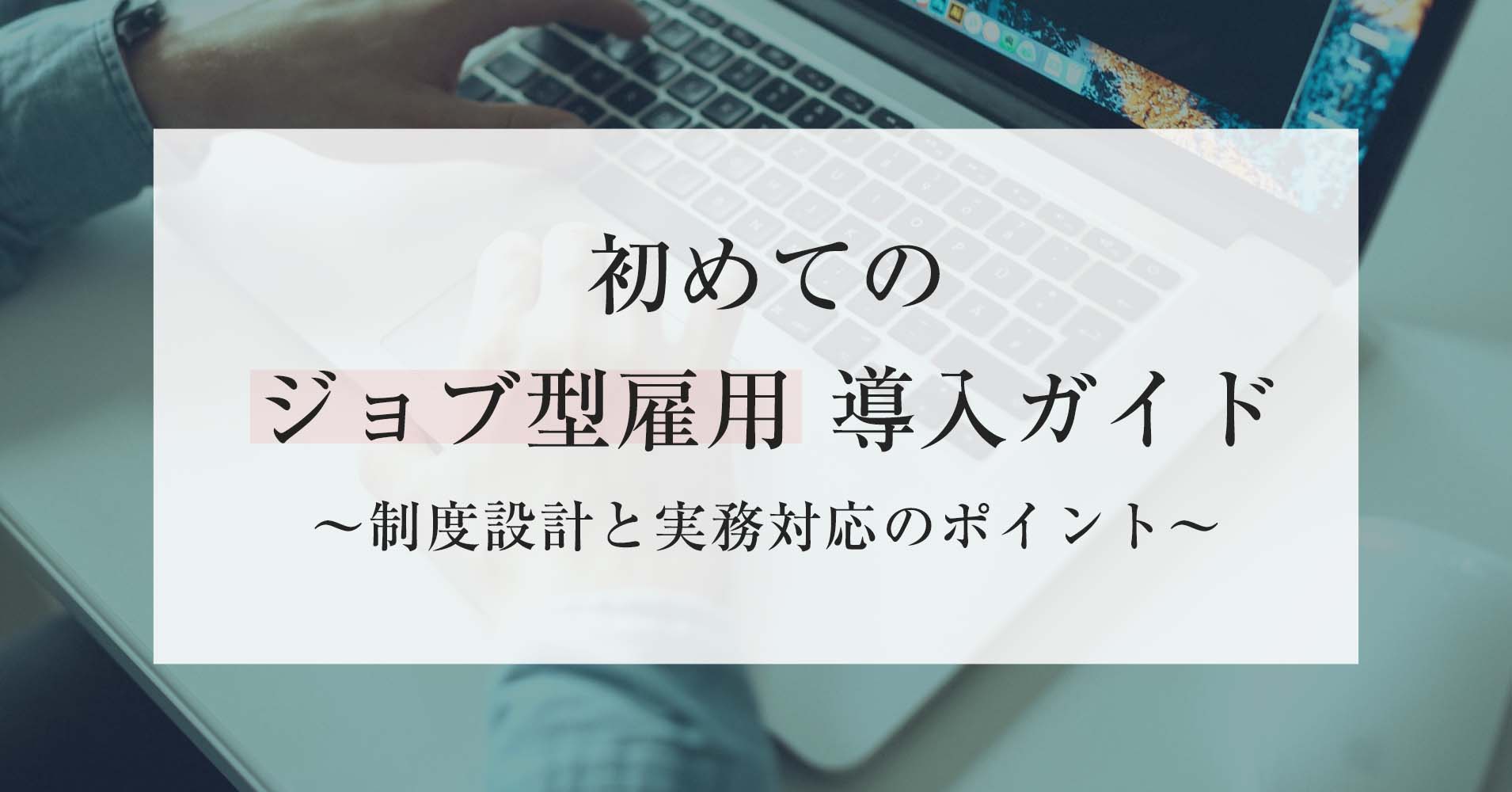
この記事の目次
注目される「ジョブ型雇用」を専門家が解説!
近年、働き方が大きく変化し、特にテレワークの普及などを背景に、多くの企業で人事管理制度の見直しが進んでいます。
その中で注目されているのが「ジョブ型雇用」です。
しかし、「そもそもジョブ型雇用とは一体何なのか」「導入にあたってどのような点に注意すれば良いのか」といった疑問をお持ちの企業担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、変化する雇用環境におけるジョブ型雇用の位置づけと、その導入にあたって留意すべき点について、労務の専門家が解説します。
ジョブ型雇用とは何か?メンバーシップ型雇用と何が違う?
日本は「メンバーシップ雇用」が主
これまで日本の多くの企業で主流となってきたのは「メンバーシップ型雇用」です。
これは、特定の職務や業務内容に限定して採用するのではなく、組織の一員(メンバー)として人材を受け入れる雇用の形態です。
労働者は入社後、配属や異動を通じてさまざまな部署や職務を経験しながら、幅広いスキルや知識を持つゼネラリスト(いろんな仕事をバランスよくこなせる、幅広い力を持った人)として育成されていきます。
この仕組みにより、企業は状況に応じて柔軟に人材配置を行うことができ、長期的に人材を育てていく土壌が築かれてきました。
一方で、どの業務を担当するかは会社の裁量に大きく依存するため、労働者にとっては仕事内容や勤務地が変わる可能性があるなど、必ずしも安定的とはいえない側面もあります。
それでも、このメンバーシップ型の仕組みが、日本企業の長期雇用慣行や年功序列と結びつき、これまで組織の安定運営や従業員の一体感を支えてきたといえるでしょう。
「ジョブ型雇用」は欧米スタイル
「ジョブ型雇用」とは、担当する職務(ジョブ)を明確に定めた上で労働者を採用し、スペシャリストとしての活躍を促す人事管理制度です。
ジョブ型雇用においては、職務記述書(ジョブディスクリプション)が重要な役割を果たします。
この職務記述書には、職務内容、責任の範囲、その職務に必要なスキルや経験、さらには勤務時間や勤務場所などが詳細に明記されます。
そして、報酬は、労働者の職務遂行能力に基づく職能給ではなく、それぞれの職務の市場賃金に連動した職務給(職務等級制度)、つまり職務内容や成果によって決定されることになります。
ジョブ型雇用は今、日本で確実に広がっている
ジョブ型雇用は、欧米では古くから標準的な雇用制度ですが、日本では2020年に経団連が導入を推奨したことなどをきっかけに、大企業を中心に広がりを見せています。
特に、社員一人ひとりの業務状況の把握が困難になりがちなテレワークにおいては、仕事の成果に基づく処遇への転換が求められるため、職務・職責が明確なジョブ型の人事管理制度が適している側面があると言えます。
ジョブ型雇用のメリットとデメリット
ジョブ型雇用を導入することで、以下のようなメリットとデメリットが考えられます。
メリット
■特定の職務に必要な専門分野に強い人材を採用・育成しやすくなる。
■社員は担当する職務に専念できるため、専門性を高めやすい。
■職務範囲や責任が明確になることで、不要な業務を減らし、業務効率化や生産性の向上につながりやすい。
■テレワークなど、多様な働き方にも適している。
デメリット
■職務が限定されるため、配置転換や転勤、柔軟な職務の追加が難しくなる。
■担当する職務がなくなった場合、社員が解雇されるリスクがある。
■ゼネラリストとして幅広いスキルを育成することが難しくなる。
■職務によっては、日本国内で適切な人材を確保するのが困難な場合がある。
■会社への帰属意識が薄れやすく、チームワークの醸成が難しくなることがある。
ジョブ型雇用の導入にあたって特に留意すべき点
ジョブ型雇用を成功裏に導入し、運用していくためには、いくつかの重要な留意事項があります。
1. 職務内容の明確化と適正な目標設定
ジョブ型雇用では、報酬が職務の成果に基づいて支払われます。
そのため、職務ごとの内容を明確にし、適切な目標を設定することが不可欠です。
これまでの日本企業では、職務内容が曖昧で目標設定も不十分なケースが多く、成果中心の目標管理の基盤が整っていないのが現状です。
ジョブ型雇用では、職務記述書を作成し、職務内容や責任範囲、必要な能力・経験を詳細に定めることが大切です。
これにより、適正な目標設定とその管理が可能になります。
2. 賃金体系・評価制度の構築
ジョブ型雇用の賃金体系は、年功序列の職能給ではなく、成果に応じた職務給(職務等級制度)であることが重要です。
職種や責任範囲を見極め、適切な賃金額を設定する必要があります。
また、その賃金は労働市場での職務の価値(市場評価賃金)に見合った水準でなければなりません。
市場価値より低い水準では、優秀な人材が他社に流出するリスクが高まります。
さらに評価制度も、職務記述書に基づき、成果に対して定量的で具体的な基準を設ける必要があります。
これにより、職務の能力に応じた報酬を正しく支払う仕組みが機能します。
3. 配置転換・転勤の取り扱い
ジョブ型雇用は、職務内容を限定した労働契約です。
そのため、原則として労働者の同意なしに職務内容を変える配置転換や転勤を命じることはできません。
会社が一方的に配置転換を命じる場合は、労働契約の変更として労働者の同意が必要です。
最高裁判例(滋賀県社会福祉協議会事件)でも、職種や業務を特定の人に限定する合意がある場合には、使用者が労働者の同意なしに合意に反する配転を命じる権利はないと示されています。
また、労働契約の締結時や有期契約の更新時には、就業場所や業務内容の「変更の範囲」を明示することが、労働基準法施行規則で義務付けられています。
ジョブ型導入はリスク管理が重要。社労士に任せて安心
ジョブ型雇用、成功のカギは職務設計にあり
ジョブ型雇用は、年功序列や勤続年数に比例した評価ではなく、担当する職務やその遂行状況を基準に評価する制度です。
技能や知識の高い専門人材の確保に適しており、テレワークのような柔軟な働き方とも相性が良いという特徴があります。
しかし、その導入には、職務記述書を用いた職務内容の明確化が不可欠です。
さらに、評価の透明性や正当性を確保するための制度設計も求められます。
また、職務がなくなった場合に会社都合で一方的に配置転換を行うことが難しくなるなど、これまでの雇用システムとは大きく異なる点があることを十分理解しておく必要があります。
ジョブ型雇用の導入を検討する際には、自社の現状をしっかり整理・分析し、どの職種に導入できるのかを慎重かつ丁寧に見極めていくことが重要です。
ジョブ型雇用導入には専門家へご相談を
とはいえ、就業規則や賃金規程、評価制度の整備まで含めると専門的な知識や実務経験が不可欠であり、社内だけで完結するのは簡単ではありません。
当社は、これまで数多くの企業様の制度設計や運用をサポートしてきた実績があります。
自社に最適な形でジョブ型雇用を導入し、将来のリスクを回避しながら運用していくためにも、ぜひ一度、労務のプロフェッショナルである社労士法人アーチスにご相談ください。
こんな記事も読まれています
プロフィール

神奈川県平塚市
社会保険労務士法人・行政書士法人
アーチス
労務に関わる手続き・問題から助成金まで、幅広くお問い合わせに対応していますのでどうぞ安心してご相談ください。
関東エリアを中心に遠方のお客様はZOOMミーティングにより全国どこからでもリモートでのご対応が可能。
20人以上の専門性を持ったスタッフが対応を手厚く、よりスピーディーに行います。