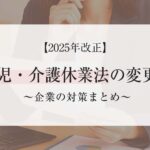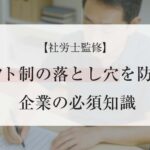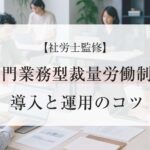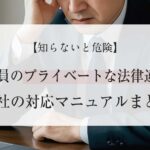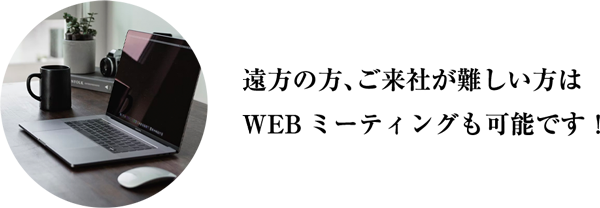従業員のプライベートな法律違反!会社の対応マニュアルまとめ
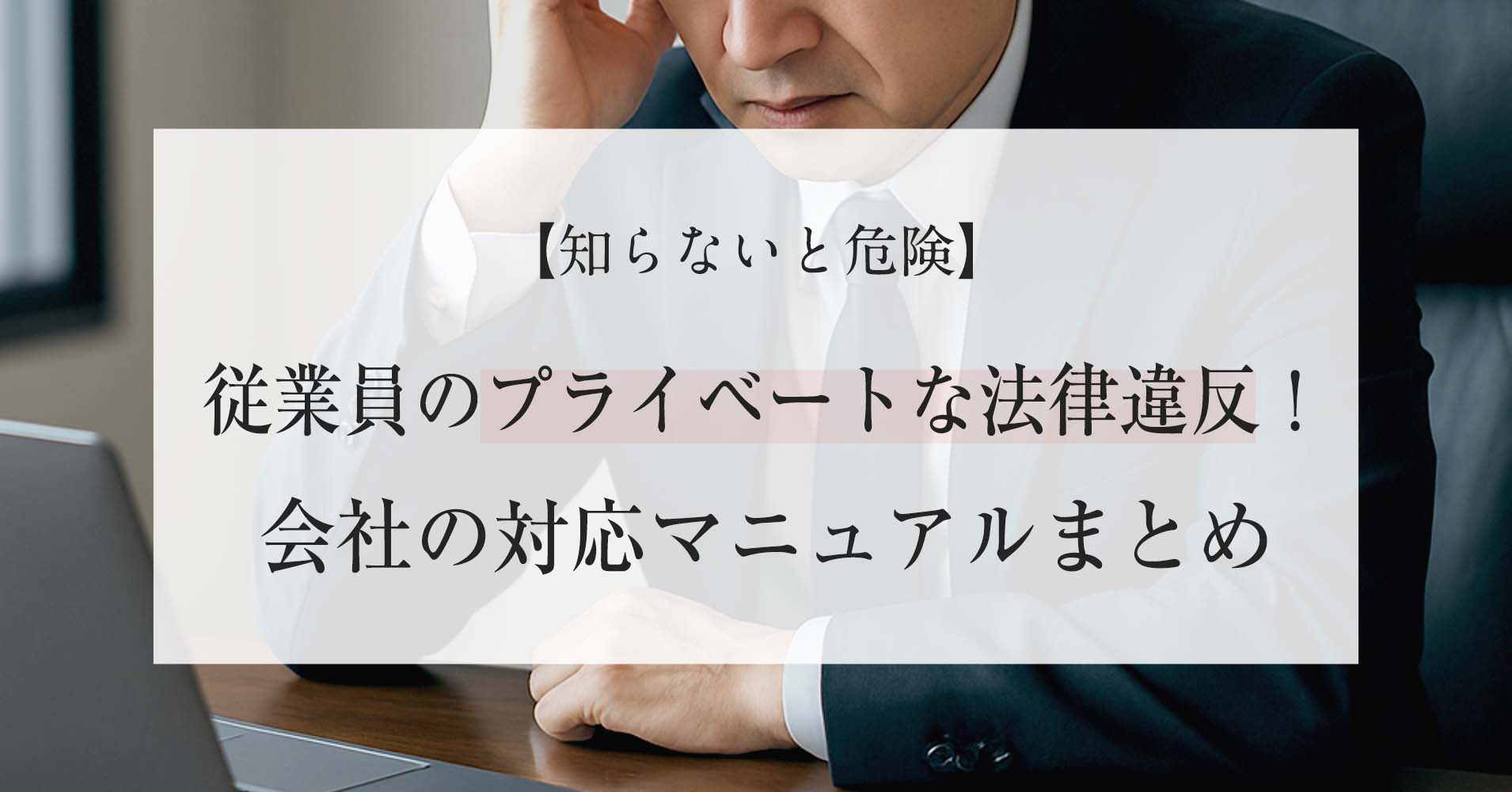
この記事の目次
適切な対応、避けるべき行動、そして効果的な予防策
従業員の違法行為は、企業にとって“待ったなし”のリスクです。
対応を誤れば、社会的信用の失墜だけでなく、法的責任を問われる可能性もあります。
近年は、オンラインカジノの利用や交通違反による免許停止といった「一見プライベートな問題」が、SNSや報道で瞬時に拡散し、会社全体が社会的非難の矢面に立つ事例が増えています。
「従業員の私生活だから」と見過ごすのは、もはや企業にとって危険な選択です。
本記事では、違反が発覚した際に企業がどう動くべきか、絶対に避けるべき対応は何か、そして信用失墜を未然に防ぐ危機管理体制の整え方について、専門家の視点から具体的に解説します。
「何を知り、どう動くか」発覚時の適切な対応
従業員のプライベートでの法律違反が疑われる、または発覚した場合、企業は迅速かつ適切に対応する必要があります。
発覚ルート別にみる初動対応のポイント
従業員の法律違反は、社内外のさまざまなルートから発覚する可能性があります。
内部通報制度や上司への報告といった社内経路に加え、警察やマスコミといった社外からの連絡によって、突然会社が対応を迫られるケースも少なくありません。
発覚経路ごとに適切な初動対応を取れるかどうかで、企業リスクは大きく変わります。ここでは、主な発覚ルート別の留意点と実務上の対応の考え方を整理します。
•内部公益通報窓口からの通報
公益通報者保護法に基づき、通報者保護に最大限留意しつつ、必要な調査を実施します。法令違反が明らかになれば、速やかに是正措置をとる必要があります。
•その他の社内ルート(上司への報告、人事部への通報など)
法令やガイドラインで義務付けがなくても、社内秩序の乱れや不正行為誘発の可能性を考慮し、事実関係の調査を進めるべきです。
•社外ルート(警察・捜査機関、マスコミ、取引先など)
警察からの連絡は捜査協力要請であるため、協力する方向で対応します。
マスコミからの取材には、社内調査を先行させ、安易な回答は避けるべきです。
•社内アンケートの実施
通報がない場合でも、コンプライアンス上のリスク回避のため、会社から積極的に社内アンケートを実施することも有効です。
正直な申告を促すため、限定的な情状酌量の措置を提示することも一案です。
事実関係をどう確認するか -調査の基本と留意点-
従業員の法律違反が疑われる場合、対応の前提として欠かせないのが「事実関係の正確な把握」です。
しかし、証拠を集める手段によってはプライバシー侵害や違法調査にあたるリスクもあり、企業には慎重な判断が求められます。
ここでは、会社貸与デバイスの調査、関係者や本人へのヒアリング、そして自己所有デバイスの場合の限界など、主な調査手法と実務上の留意点を解説します。
•会社貸与のPC・スマートフォン
従業員が会社貸与のPCやスマートフォンからオンラインカジノなどに参加していた場合、業務命令によりこれらを返還させ、履歴を調査することが考えられます。
就業規則にモニタリング規定があればスムーズですが、規定がない場合でも、刑法犯に関わる調査は必要性が高く、プライバシー保護の必要性も低いことから、モニタリングが有効となる可能性は高いとされています。ただし、個人情報保護法に基づく利用目的の特定や公表・通知、利用制限に留意が必要です。
•ヒアリング
直属の上司や同僚からの目撃情報のヒアリング、借金状況や私生活に関する周囲からのヒアリングも重要です。これらの情報収集後、当該従業員本人からヒアリングを行います。
•自己所有デバイスの場合
従業員が自己所有のPCなどを使用している場合、会社が直接客観的証拠を収集することは困難です。周囲からのヒアリングが中心となります。
違反が明らかになったとき、企業が取るべき対応とは
従業員の法律違反が事実として判明した場合、企業は「どこまで介入すべきか」「どのような処分が妥当か」という難しい判断を迫られます。
安易な対応は、刑事責任の見落としや逆に名誉毀損リスクを招く恐れがあり、処分の過不足は社内秩序や企業イメージに直結します。
ここでは、刑事・法的対応の検討、懲戒処分の可否、交通事故や免許停止といった事例ごとの対応、そして安全配慮義務の範囲など、企業が踏まえるべき主要なポイントを整理します。
刑事・法的対応の検討
•従業員への自首の奨励
従業員に自首を促すことが考えられます。
•会社からの刑事告発
後日、会社が意図しない形で情報が公表されるリスクを避けるため、会社から刑事告発を検討するケースもあります。
•社内外への公表
通常は捜査機関の捜査結果を待ってからで良いと考えられます。
無罪推定の原則や、会社が名誉毀損等のリスクを負う可能性があるためです。
ただし、従業員が事実を認めており、証拠が十分な場合には、早期の報道リスクを考慮して刑事告発と同時に公表することも考えられます。
懲戒処分の検討
従業員のプライベートでの行為は、原則として懲戒処分の対象とはなりません。
しかし、「職場内における秩序ないし規律の維持に障害をもたらす場合」や「対外的に企業の社会的地位ないし信用を失墜せしめたことが客観的に認められる場合」には、懲戒の対象となり得ます。
オンラインカジノの利用
•就業時間中・職場内での利用
職務専念義務違反を理由とした懲戒処分が考えられます。
•休憩時間中・就業時間外での職場内利用
一人で利用した場合は直ちに企業秩序を乱したとは言いがたいですが、他の従業員を巻き込んだり、借金トラブルに発展したりした場合は企業秩序を乱したと認定される可能性があります。
特に管理監督的地位にある者の関与や、不正行為との関連がある場合は、より重い処分も検討されます。
•私生活上での利用
原則として直ちに懲戒事由とはなりません。しかし、オンラインカジノ利用が発覚し、それが報道されるなどして企業の信用を失墜させた場合には懲戒が可能になります(芸能人や有名企業などで顕著)。
•虚偽申告
事実を否定する虚偽の申告は、会社を誤った方向に導き、重大な結果を招く可能性があるため、重大な非違行為として懲戒の対象となり得ます。
•違法性意識の薄さ
従業員に違法性の意識が薄い場合でも、刑法上は原則として罪は成立します。
懲戒処分を検討する際には、警察がオンラインカジノを違法と告知した時期(令和4年10月)以降の行為に限定する、あるいは社内での注意喚起後の行為に限定することも考えられます。
プライベートでの交通事故による免許停止
•配置転換の可能性
職務専念義務違反を理由とした懲戒処分が考えられます。
•休憩時間中・就業時間外での職場内利用
当社の営業職員が勤務時間外の交通事故で免許停止となったケースでは、車を運転する必要がない事務職への配置転換が検討されています。
就業規則に業務上の都合による配置転換の定めがあり、職務内容限定の合意がない場合は、会社に広い裁量が認められ、労働者の同意なしに配置転換が可能です。
この場合も、配置転換が権利の濫用にあたらないことが重要です。
•権利濫用とならない条件
業務上の必要性(免許停止により営業業務に支障が出ること、交通事故のリスク等)、不当な動機・目的がないこと、従業員に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせないこと、などが判断基準となります。
給料の一定程度の低下は一般的に問題視されにくいですが、転居を伴うなど著しい不利益が生じる場合は注意が必要です。
•職務内容限定の合意がある場合
原則として、配置転換はその合意の範囲に限定されます。
この範囲を超えて配置転換を行う場合は、従業員に十分に説明し同意を得ることが適当と考えられます。
•将来的な復帰の検討
免許停止期間が終了し、一定の教育・研修により交通安全意識が改善された後、本人の意思も踏まえて営業職への復帰の機会を与えることもあり得ます。
安全配慮義務の範囲
従業員の私生活上の行為に対して、会社に安全配慮義務が及ぶとは限りません。
しかし、取引先が絡むなど、業務上の行為と私生活上の行為の境界が曖昧な場合は、慎重な事実調査が必要です。
賭博事案では反社会的勢力が関与する可能性もあるため、警察や弁護士などの専門家に委ねることが妥当です。
行ってはいけない対応
•十分な調査なしでの性急な処分
憶測や不確かな情報に基づいた処分は、後々トラブルの原因となります。
•従業員のプライバシーの過度な侵害
私的利用のデバイスや通信内容の不当な監視は、プライバシー権侵害となる可能性があります。
•不当な転居を伴う配置転換
合理的な理由なく、従業員に著しい不利益を与える転居を伴う配置転換は、権利の濫用とみなされる可能性があります。
•懲戒解雇の安易な適用
軽微な私的行為や、職場秩序・企業信用への影響が少ない行為に対して即座に懲戒解雇を適用することは、無効と判断されるリスクが高いためです。
トラブルを未然に防ぐために-未来を見据えた予防策-
従業員のプライベートでの法律違反を防ぐためには、事後対応だけでなく、予防的な取り組みも不可欠です。
•就業規則等での明確な定めと周知
憶測や不確かな情報に基づいた処分は、後々トラブルの原因となります。
•コンプライアンス研修・啓発活動
オンラインカジノが日本国内から利用すると違法であることなど、従業員の違法性意識が薄い問題について、定期的な研修や注意喚起を行うことが有効です。
また、交通安全意識の向上も図るべきです。
•信頼できる内部通報窓口の設置
従業員が問題を発見した場合に安心して通報できる窓口を整備し、通報者保護を徹底することで、早期発見につながります。
•社内アンケートの活用
定期的に社内アンケートを実施し、従業員のプライベートな行動が会社に与える影響について意識を促すことで、潜在的なリスクを把握し、自発的な申告を促すことができます。
「もしかしたら…」と思ったら、ぜひ早めにご相談を!
従業員のプライベートでの法律違反は、どの企業にも起こり得るリスクです。
しかも一度発覚すれば、SNSや報道を通じて一気に拡散し、信用失墜や取引停止といった深刻なダメージにつながりかねません。
「社内で何とか対応できるだろう」と甘く見てしまうと、初動を誤り、取り返しのつかない状況に発展する恐れがあります。
だからこそ、トラブルが起きる前に就業規則や研修体制を整えること、そして発覚時には即座に専門家へ相談することが不可欠です。
わたしたちアーチスは、労務の専門家として数多くの企業の危機対応や制度設計をサポートしてきた実績があります。
「もしかしたら…」と思われたら、ぜひ早めにご相談ください。
早い一歩が、会社を守る最大の防御となります。
こんな記事も読まれています
プロフィール

神奈川県平塚市
社会保険労務士法人・行政書士法人
アーチス
労務に関わる手続き・問題から助成金まで、幅広くお問い合わせに対応していますのでどうぞ安心してご相談ください。
関東エリアを中心に遠方のお客様はZOOMミーティングにより全国どこからでもリモートでのご対応が可能。
20人以上の専門性を持ったスタッフが対応を手厚く、よりスピーディーに行います。