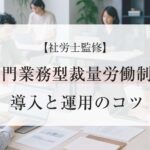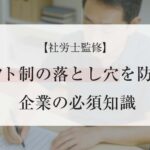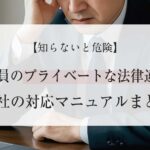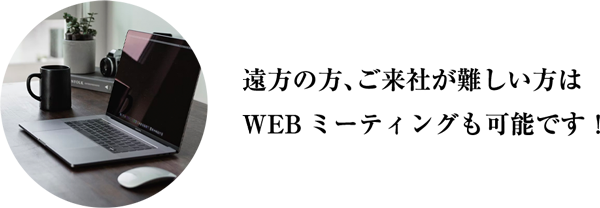【知らないと危険!】従業員の身だしなみ規定と企業のリスク管理
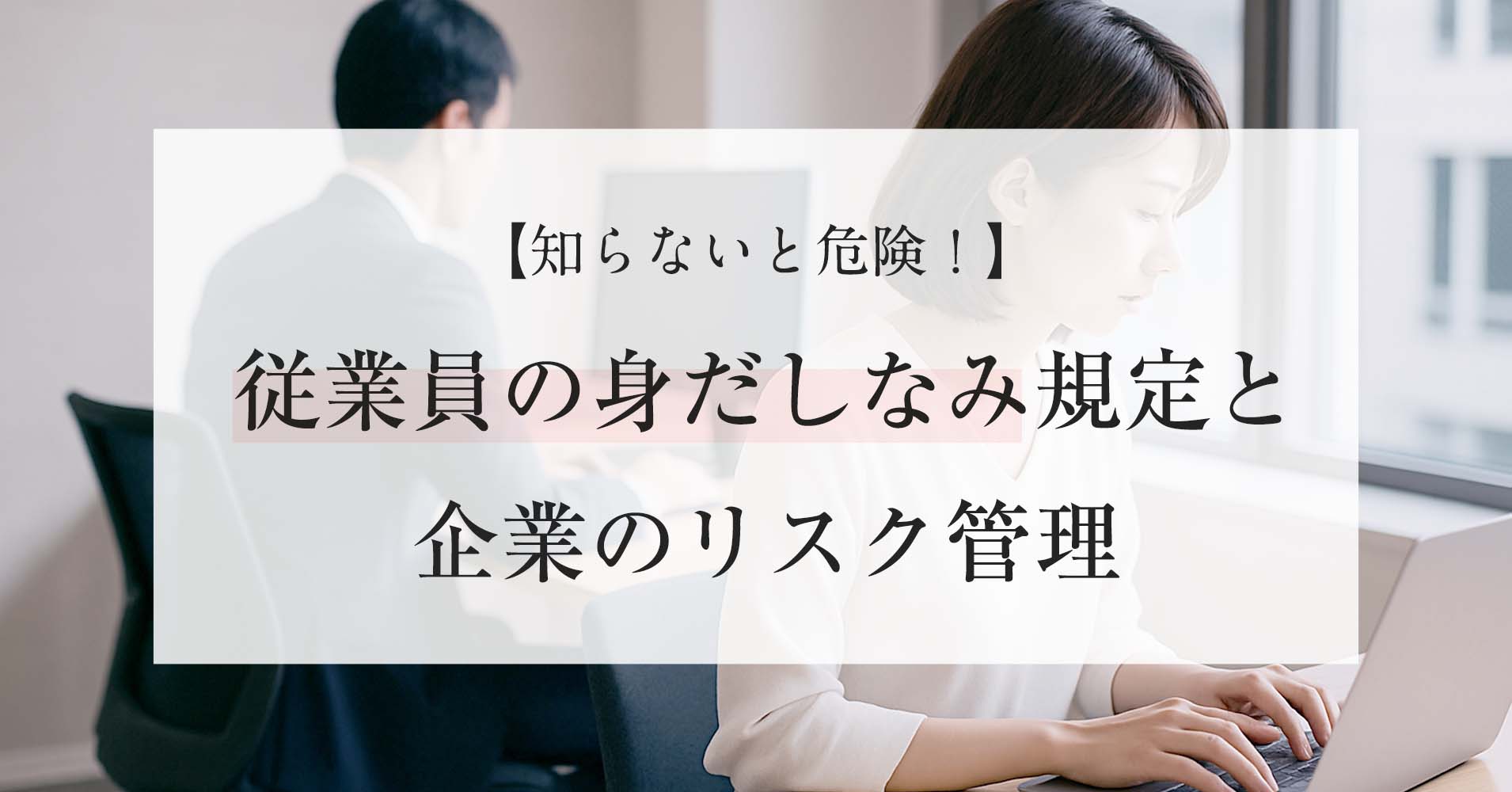
この記事の目次
従業員の身だしなみ規定について、リスクと対応を理解しよう
企業の秩序維持と円滑な業務遂行のため、従業員の身だしなみに関する規定を設けることは多くの会社で行われています。
しかし、髪型やひげ、服装といった身だしなみは、個人の人格や自由に関する重要な事柄であり、労働者の自己決定権(日本国憲法13条の幸福追求権の一部)として保障されています。
このため、企業が身だしなみ規定を設ける際には、安易な規制は違法リスクを伴うことから、会社の規制と従業員の自由権との調整が不可欠です。
本記事では、判例や最新の社会動向を踏まえつつ、企業が身だしなみ規定を策定・運用する上で知っておくべき法的リスクと対応策を解説します。
身だしなみ規定が有効となる「必要性・合理性」とは
企業が身だしなみ規定を設定し、従業員に遵守を求めることは、企業秩序を維持する観点から一般的に認められています。
特に、窓口業務や接客業のように従業員の身だしなみが重要な意味を持つ業種では、髪型、ひげ、服装などを制限する規定が設けられることがあります。
しかし、その制限は無制限に許されるものではありません。
判例が示す基本的な考え方
判例では、身だしなみ規定は、労働者の自由を制限するものである以上、「企業の円滑な運営に必要かつ合理的な範囲」でのみ有効とされています。
「制限の必要性」
「合理性」
「手段の相当性」
この3点が基準とされ、業務や顧客対応の有無によって許容範囲が大きく変わります。
例えば、接客業や窓口業務など、外見が顧客の印象に直結する職種では、髪型や服装に一定の規律を設ける合理性が認められます。
一方で、外部との接点がない事務職などでは、厳しい制限を設ける合理性は乏しいとされています。
規定には従業員の自由と会社の定めとの調和が重要であり、労働者の選択が著しく非常識である、または当該業種における一般的慣行に反し、業務に支障を来す恐れがある場合に限り、身だしなみ規制を受け入れる必要が生じると考えられています。
裁判例から見る身だしなみ規定の限界
大阪メトロの「ひげ訴訟」
大阪市交通局(現・大阪メトロ)の事例では、運転士らが「ひげを理由に人事評価を下げられ、給与を減額された」ことを争いました。
大阪高等裁判所(平成30年7月6日判決 -労判1187号-)は、清潔感を求める身だしなみ規定自体は職務上の合理性があるとしながらも、「ひげそのものを理由に減点・減給する運用は裁量権の逸脱・濫用で違法」と判断しました。
この判例は、規定そのものが認められても、過度な運用は違法となり得ることを示す重要な事例です。
その他の事例:髪色・ピアス・タトゥー
•髪色(茶髪禁止)
労働者を直接対象とした判例は少ないものの、大阪府立高校における「茶髪訴訟」(大阪地裁令和2年10月15日判決、その後控訴審で和解)では、生徒の髪色強制をめぐり人権侵害が争点となりました。労務分野でも、職務上の必要性が乏しい髪色制限は違法と判断される可能性があると考えられています。
•タトゥー
大阪市職員タトゥー訴訟(大阪高裁平成29年9月14日判決、労判1161号)は、市が職員にタトゥーの有無を申告させた調査の適法性が争点となりました。
裁判所は「タトゥーを理由に直ちに処分するのは違法」と判断しつつも、職務内容や社会的影響に応じて一定の制限が許容され得ると示しました。
民間企業においても、接客業など顧客の印象が重視される業種では、見える部位のタトゥー制限に合理性があると考えられます。
•ピアス
ピアスに関しては、食品衛生法や労働安全衛生法に基づくガイドラインにより、食品製造現場や工場など異物混入や安全事故の恐れがある職場では、着用制限に十分な合理性が認められます。
裁判例においても、業務上の安全・衛生を確保する目的であれば、一定の身だしなみ制限は適法と判断される傾向があります。
したがって、業務特性に即したピアス制限は、企業秩序維持の観点から正当と評価されます。
企業として「行うべき対応」:バランスの取れた運用
身だしなみ規定を有効に機能させ、かつ従業員の権利を尊重するためには、以下の点に留意して対応すべきです。
業種・職務内容に応じた合理的な規定
規定は、業種や職務の特性に合わせて設計する必要があります。接客・安全管理・衛生管理が重視される業務では厳格な規定が合理的ですが、そうでない場合には最低限にとどめるべきです。
体的なマニュアルと段階的指導
どのような身だしなみが不適切であるかを具体的に示したマニュアルを作成し、従業員に周知することが望ましいです。
違反があった場合も、まずは口頭注意 → 書面注意 → 懲戒の順に、段階を踏むべきです。
多様性・ダイバーシティへの配慮
近年は「ビジネスカジュアル」や「クールビズ」が普及し、企業の服装規定も柔軟化しています。
また、宗教的背景によるスカーフ着用、LGBTQ+に配慮した性表現の自由、障害特性に伴う外見上の事情など、多様性への理解を欠いた一律規制は差別リスクを招きかねません。
企業は、社会的な受容性や人権意識の高まりを踏まえて、時代に即した規定運用を行う必要があります。
柔軟な対応は、長期的な雇用関係の安定と信頼関係の構築につながります。
企業として「行ってはいけない対応」:法的リスクを招く行為
一方で、以下のような短絡的または過度な対応は、法的トラブルを招く可能性が高くなります。
安易な一律禁止や懲戒処分
男性のひげの一律禁止は原則として認められません。
判例では、「顧客に不快感を与えるようなひげ」に限定的に解釈されており、ひげそのものが不快感を与えるわけではないとの判断が根底にあります。
違反があった場合に、短絡的に人事評価を落とし、懲戒処分ともいうべき賃金の減額を行うことは避けるべきです。
不当な人事評価や賃金減額
大阪メトロの事例では、身だしなみ規定の制定自体は必要性・合理性から認められたものの、ひげを生やしていたことを理由に人事評価を減点し、給与を減額した運用は「裁量権を逸脱・濫用したもの」であり、違法と判断されました。
適切な評価を受ける権利を侵害したとみなされるため、厳に慎むべきです。
過度な規制による採用への影響
あまりに厳しい身だしなみ規制は、従業員に息苦しさを感じさせ、「働きにくい会社」という印象を与えます。
人材確保に悪影響を及ぼすという側面も考慮すべきです。
トラブルを未然に防ぐ「予防策」
身だしなみに関するトラブルを未然に防ぐためには、以下のような予防策を講じることが重要です。
就業規則や雇用契約書への明記と周知
身だしなみ規定を導入する際は、就業規則や雇用契約書にその内容を具体的に明記し、従業員に周知し、理解と同意を得ることが重要です。
これにより、規定の透明性を高め、トラブルを未然に防ぐことができます。
継続的な見直しと社会情勢への対応
時代や社会の動き、顧客のニーズは常に変化します。規定が過剰な制約とならないよう、定期的に見直しを行うことが不可欠です。
「ビジネスカジュアル」や「多様性尊重」といった社会動向に合わせて定期的に見直しを行い、規定が時代遅れにならないようにします。
多面的な視点での制定と運用
企業の業種、社会的慣行、従業員の多様性など、複数の観点から検討し、無理のない規定を作成することが重要です。
専門家と共に、適切な身だしなみルールの運用を
従業員の身だしなみ規定は、企業の顔としての印象や企業秩序の維持に必要不可欠な要素でありながら、従業員の「自己決定権・人格的自由権」という重要な権利と深く関わるデリケートな問題です。
判例が示すように、規定自体が認められても「過度な運用」は違法とされる可能性があります。
特に、個人の自由に関する事項であるひげや髪型などを理由に、安易に不利益な人事評価や懲戒処分を行うことは、法的リスクが高い行為です。
企業としては、社会の価値観が多様化する中、規定は柔軟かつ合理的に運用し、柔軟で段階的な対応を心がけることが、従業員との信頼関係を築き、長期的・安定的な雇用に繋がると言えるでしょう。
定期的に見直すことも非常に重要です。
また、判断に迷うケースでは、社労士や弁護士と連携し、適切な制度設計・トラブル防止策を講じることが、企業と従業員双方にとって最も安全な選択となります。
万が一の際には、専門家である社労士法人アーチスにご相談ください。
こんな記事も読まれています
プロフィール

神奈川県平塚市
社会保険労務士法人・行政書士法人
アーチス
労務に関わる手続き・問題から助成金まで、幅広くお問い合わせに対応していますのでどうぞ安心してご相談ください。
関東エリアを中心に遠方のお客様はZOOMミーティングにより全国どこからでもリモートでのご対応が可能。
20人以上の専門性を持ったスタッフが対応を手厚く、よりスピーディーに行います。