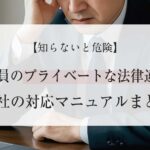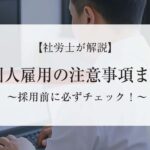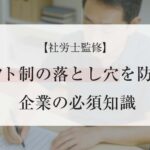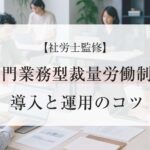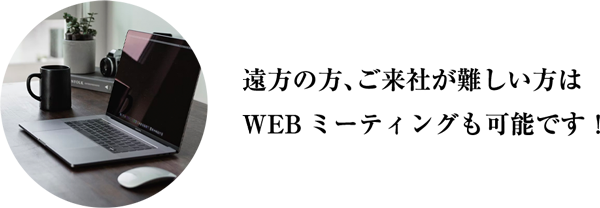2025年改正|育児・介護休業法の変更点と企業の対策まとめ
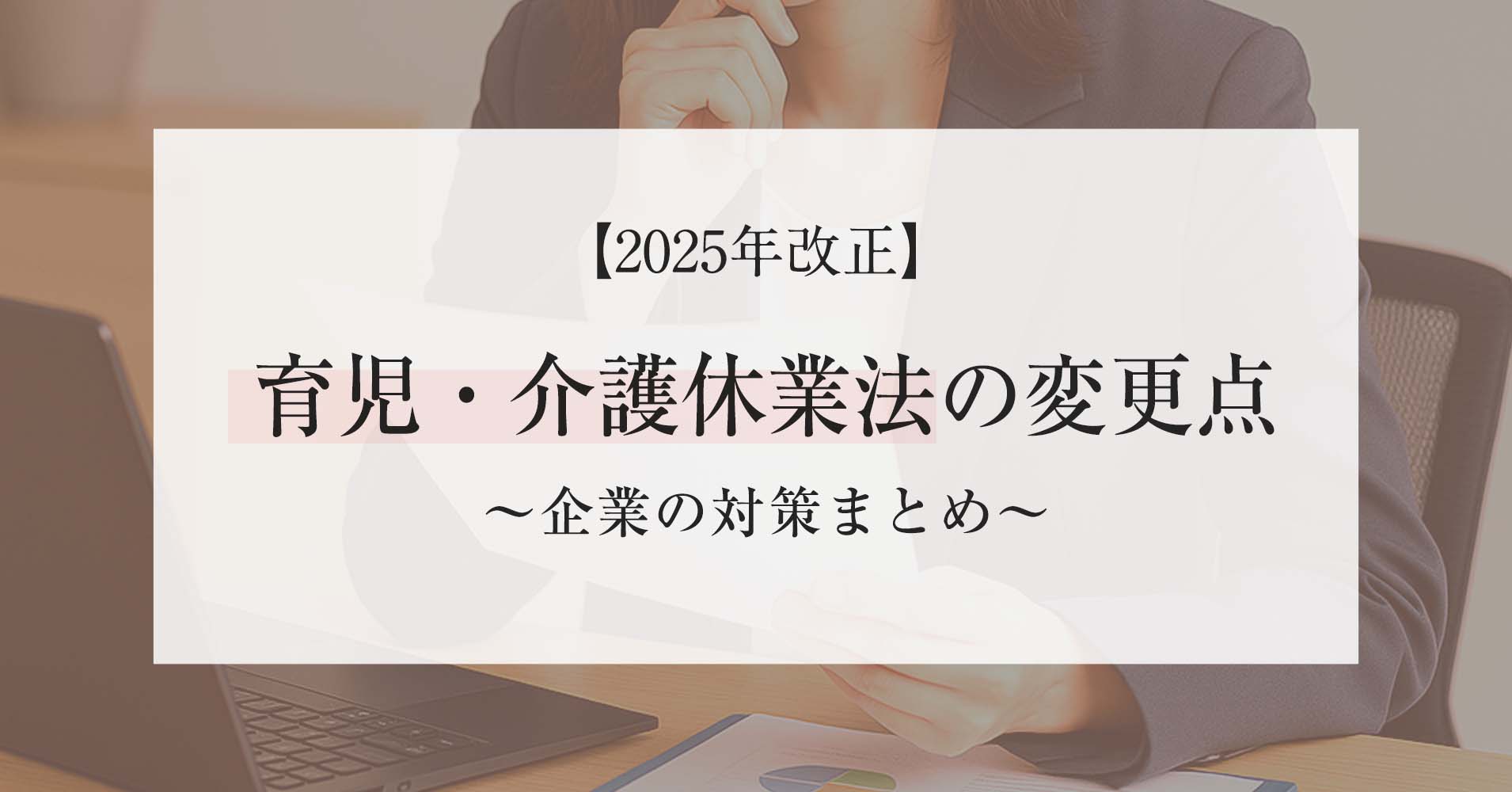
2025年には、仕事と育児・介護の両立を支援するため、育児・介護休業法が段階的に改正・施行されます。
少子高齢化が進む中、企業が優秀な人材を確保し、持続的に成長していくためには、従業員の働き方を柔軟に支える仕組みが欠かせません。
今回のコラムでは、改正の主要ポイントと企業が特に注意すべき点、そして施行までに準備すべき対応について労務の専門家の目線で解説します。
この記事の目次
育児・介護休業法改正の主要ポイントまとめ
今回の改正は、【育児】と【介護】の両面で、より柔軟な働き方を実現し、従業員が安心して制度を利用できるようにすることを目的としています。
「子の看護等休暇」の拡充
•取得対象となる子の範囲が「小学校3年生修了まで」に拡大されます。
•取得事由も「病気・けが、予防接種・健康診断」に加え、「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園・入学・卒園式」が追加されます。
•労使協定による「継続雇用期間6か月未満の従業員の除外規定」が廃止され、より多くの従業員が利用できるようになります。
残業・短時間勤務制度の対象拡大・選択肢追加
•「所定外労働の制限(残業免除)」の対象が「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大されます。
•3歳未満の子を養育する労働者の短時間勤務の代替措置に「テレワーク」が追加されます。
「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」義務化(2025年10月1日施行)
•3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、企業は「始業時刻等の変更」「テレワーク等」「保育施設の設置運営等」「養育両立支援休暇の付与」「短時間勤務制度」の5つの措置から2つ以上を選択して講じる義務が生じます。
労働者はそのうち1つを利用可能です。措置選択には事前に労働者の過半数で組織する労働組合などからの意見聴取が必要です。
「個別の意向聴取と配慮」義務化(2025年10月1日施行)
•妊娠・出産等の申出時と、3歳未満の子を養育する労働者(子が3歳になるまでの適切な時期)に対し、勤務時間や勤務地など仕事と育児の両立に関する個別の意向を聴取し、その意向に配慮することが義務付けられます。
育児休業取得状況の公表義務拡大
•公表義務の対象企業が「従業員数1,000人超」から「従業員数300人超」に拡大されます。男性の育児休業取得率などが公表対象となります。
•「介護休暇」要件緩和:育児休暇と同様に、労使協定による「継続雇用期間6か月未満の従業員の除外規定」が廃止されます。
「介護離職防止のための雇用環境整備」義務化
•事業主は、介護休業や介護両立支援制度等の利用を促進するため、「研修の実施」「相談体制の整備」「利用事例の収集・提供」「利用促進方針の周知」のいずれか1つ以上の措置を講じる必要があります(複数実施が望ましい)。
「個別の周知・意向確認」と「早期情報提供」義務化
•家族の介護に直面した旨の申出があった労働者に対し、介護休業制度等の内容、申出先、介護休業給付金について個別に周知し、利用の意向を確認することが義務付けられます。
•労働者が介護に直面する前の早い段階(例:40歳に達する年度)で、介護休業制度等に関する情報提供を行う義務が課せられます。介護保険制度についても併せて周知することが望ましいとされています。
「介護期のテレワーク導入」努力義務化
•要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主には努力義務が課せられます。
会社が気を付けるべきこと
今回の法改正は、法改正は単に制度を導入すればよいという話ではありません。
企業にとって多岐にわたる対応が求められ、運用を誤れば大きなリスクにつながります。
特に以下の点に留意が必要です。
不利益取扱いの禁止
•育児・介護休業の取得を理由とした解雇や不利益な取扱い(賞与の不支給や大幅な減額、退職金算定での不公平な除外など)は固く禁じられています。
過去の裁判例でも、休業を理由とした不利益評価は無効と判断されたケースがあります。
公平性を欠いた対応は企業の信頼を大きく損なうことになるので注意しましょう。
•賞与の算定においては、休業期間を欠勤扱いとすること自体は違法ではありませんが、全く支給しないことは「将来の意欲向上や継続勤務を期待する」という賞与の性格から好ましくありません。
退職金の算定についても、これまで算入していた育児・介護休業期間を除外することは大きな不利益取扱いとなるため、公平性を考慮し、慎重な対応が求められます。
就業規則・社内規定の見直しと合意形成
•改正内容に合わせ、就業規則や育児・介護休業規程、退職金規程などを速やかに見直す必要があります。特に労働条件の不利益変更にあたる場合は、原則として労働者の合意が必要であり、合理的な説明と書面での取り交わしが不可欠です。
•介護休業中の社会保険料は育児休業と異なり免除措置がないため、誤解を招かないよう従業員に明確に周知しましょう。
人材確保と企業イメージ
•育児・介護休業取得に対する不利益変更は、今後の優秀な人材確保において企業にとってマイナスになる可能性があります。
何より、育児・介護と仕事を両立できる環境を整えることは、人材確保の観点からも重要です。
充実した両立支援制度は、従業員満足度を高め、企業イメージ向上にも繋がります。
会社が行うべきこと
改正施行日を待ってから動き出すのでは遅すぎます。
企業は今から計画的に準備を進めていく必要があります。
社内体制の整備と周知
•2025年10月1日施行の「柔軟な働き方を実現するための措置」として、自社の業務実態に合わせて、柔軟な働き方を実現するための措置を2つ以上を選び、就業規則に明文化して従業員に周知しましょう。
•「介護離職防止のための雇用環境整備」として、相談窓口の設置、研修実施、利用事例の共有、方針の周知など、介護・育児の両立支援を後押しする雇用環境を整備します。
個別の周知・意向確認・意向聴取の実施
•従業員からの妊娠・出産等の申出時、および子が3歳になるまでの適切な時期に、対象制度の個別周知、取得意向確認、就業条件に関する意向聴取、そしてその意向を踏まえた配慮を確実に行います。
その記録は書面やメールで残しておくと安心です。
早期情報提供の徹底
•従業員が介護に直面する前(例:40歳に達する年度)に、介護休業制度や介護両立支援制度について情報提供し、早期の備えを促すことが求められます。
制度の整備だけでなく「計画的な周知」が重要になります。
計画的なスケジュール管理と専門家への相談
•施行日(2025年4月1日、10月1日)までに、就業規則の改定、労使協定の締結、意見聴取、社内書式の整備、従業員への説明会など、多岐にわたる準備を計画的に進めることが重要です。
企業が準備すべきチェックリスト(2025年版)
□ 就業規則・社内規程を最新化したか
□ 労働者代表からの意見聴取を実施したか
□ 制度内容を従業員へ周知徹底したか
□ 妊娠・出産・介護時の個別対応フローを整備したか
□ 介護離職防止の体制を設けたか(窓口・研修・事例共有)
□ 男性育休取得率を把握・改善しているか
□ 助成金・補助金の活用を検討したか
よくある質問(FAQ)
Q1. 男性社員の育児休業取得も対象ですか?
はい。男性も含めすべての労働者が対象です。2025年改正では男性育休取得率の公表義務も広がります。
Q2. 300人未満の中小企業は対象外ですか?
いいえ。公表義務の一部は300人以上が対象ですが、柔軟な働き方措置や意向聴取義務は全企業に適用されます。
Q3. 違反するとどうなりますか?
厚労省の勧告・指導や企業名公表など行政処分の対象となります。企業イメージや採用活動にも大きな影響が出ます。
Q4. 就業規則は必ず改定が必要ですか?
はい。改正法に対応していない規程はトラブルの原因になります。速やかな改定が不可欠です。
Q5. 助成金を使えますか?
「両立支援等助成金」など、制度導入費用を補助する仕組みがあります。特に中小企業は積極活用が有効です。
見落としは企業の信用失墜に直結、確実な準備を
今回の育児・介護休業法改正は、単なる制度変更ではなく、企業文化そのものを変える大きな一歩となります。従業員が安心して長く働ける環境を整えることは、結果的に企業の競争力を高めることにつながります。
しかし、制度設計や就業規則の改定、労使協定の整備、助成金の活用など、専門知識がなければ見落としや誤解も生じやすく、結果的に法違反やトラブルにつながりかねません。
社労士法人アーチスでは、最新の情報とスピード感を持って、法改正に伴う対応支援、規程見直し、従業員説明会の実施など、貴社の状況に応じた最適なサポートを提供しています。
改正法の円滑な導入と人材定着を実現するためには、専門家によるサポートが安心です。
今のうちから準備を始め、安心できる職場環境を一緒に整えていきましょう。
こんな記事も読まれています
プロフィール

神奈川県平塚市
社会保険労務士法人・行政書士法人
アーチス
労務に関わる手続き・問題から助成金まで、幅広くお問い合わせに対応していますのでどうぞ安心してご相談ください。
関東エリアを中心に遠方のお客様はZOOMミーティングにより全国どこからでもリモートでのご対応が可能。
20人以上の専門性を持ったスタッフが対応を手厚く、よりスピーディーに行います。