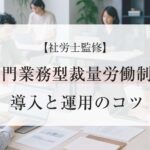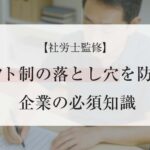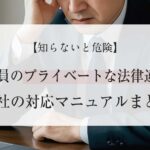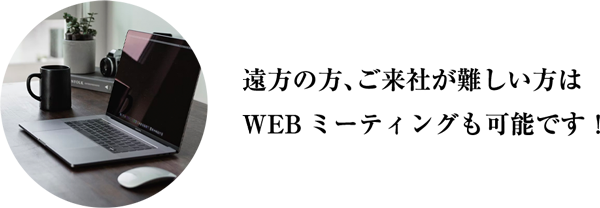シフト制の落とし穴を防ぐ!企業の必須知識
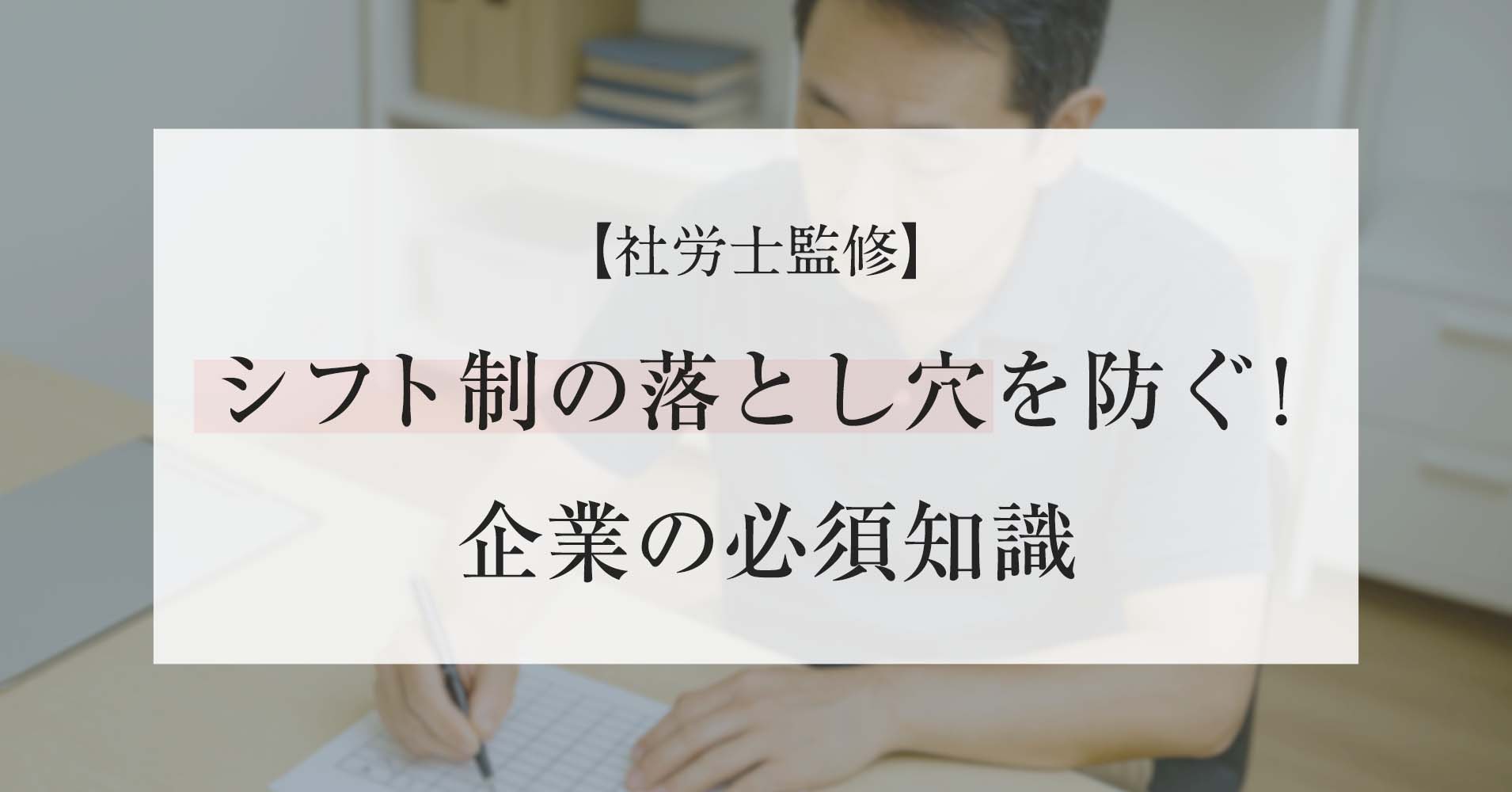
Q: 当社では人手不足を解消するため、シフト制のアルバイトを多数雇用する予定です。労働契約を結ぶ際や実際にシフトを組むにあたり、どのような点に注意すればよいでしょうか?
このようなシフト制のお悩みは、当社にもよく頂きます。
人手不足の中で、シフト制を活用して柔軟な働き方を導入する企業が増えています。
一方で、「シフトが急に変えられた」「出勤を拒否された」といったトラブルが起きやすいのも事実です。
原因の多くは、採用時やシフト作成時に労働条件が曖昧なまま運用されていること。
特に、勤務日や時間の取り決めが不明確だと、後の紛争に発展するリスクがあります。
この記事では、シフト制を導入・運用する際に会社が必ず押さえておくべき注意点を、実務の専門家の視点から整理して解説します。
この記事の目次
シフト制とは?
シフト制とは、労働契約の締結時点では具体的な労働日や労働時間を確定せず、一定期間(1週間・1か月など)ごとに作成される勤務シフトによって初めて労働日・労働時間が決まる勤務形態を指します。
業務の繁閑に応じて柔軟に人員配置ができるという企業側のメリットと、働く側も自分の都合に合わせて勤務を調整できるというメリットを併せ持ちます。
ただし、「シフト制」という言葉は、企業によって三交替勤務や運送業の配車スケジュールなどを指す場合もあります。
本コラムでは、「労働日・労働時間をあらかじめ確定しないタイプのシフト制」に焦点を当てて解説します。
【企業目線】ポイントを知ってトラブルを防ごう
多様な働き方の広がりや人手不足への対応として、シフト制勤務を導入する企業は増えています。
特にパート・アルバイトを中心に、一定期間ごとに労働日や時間を調整する形態が一般的です。
しかし、その柔軟さの裏側で、労働条件の認識のずれやシフト削減トラブルが起こりやすいのも現実です。
トラブルを防ぐには、制度設計と運用の両面で「明確さ」と「公正さ」を確保することが欠かせません。
今回は、企業がシフト制を導入・運用する際に押さえておくべき実務上のポイントと、トラブルを未然に防ぐための対応策を整理してご紹介します。
シフト制にまつわる主なトラブル事例
シフト制は柔軟な働き方を実現する一方で、労働条件の曖昧さから以下のようなトラブルが発生しやすくなります。
一方的なシフト削減によるトラブル
特に新型コロナウイルス感染症の拡大期には、飲食店などで営業時間の短縮や休業が迫られ、パート・アルバイトのシフトが一方的に削減されるケースが問題となりました。
会社側としては、業務がない以上、労働に来てもらっても仕事がないという事情があり、業務の繁閑に応じて労働力を調整するためにシフト制を採用している側面もあります。
しかし、従業員側、特にその会社からの収入で生活している場合、シフトが大幅に削減されると生活が困難になります。この際の労使双方の言い分は以下の通りです。
雇用契約書ですべて「シフトで定める」という記載になっていた例
•会社側の主張
雇用契約書に「毎月の労働日数、労働時間はシフトで決まる」と明記されており、労働日「0」は契約に違反しない。労働者の希望は確約ではない。
•従業員側の主張
採用時に週3日勤務を希望し、実際に3年間そのように勤務してきた。週3日は働ける契約だったはず。
•有給休暇に関する議論
シフトが「0」であるため、労働日がない以上、有給休暇も取得できないと会社側が主張するケースも発生しました。
雇用契約書で労働日(休日)、労働時間等が一部明確になっていた例
例えば、「労働日は月・水・金で、労働時間帯はシフトで決める」となっていた場合や、「週3日~で、シフトで定める」となっていた場合です。
この場合、少なくとも雇用契約で明確になっている範囲では、会社はシフトを組む義務があり、その部分については
・休業手当の支給
・年次有給休暇の取得
が認められる可能性が高まります。
これらのトラブルは、雇用契約時にどこまで労働条件を明確にするか(しなければならないか)という問題に起因します。
契約が明確であれば紛争は減る一方で、柔軟な働き方のメリットが失われる可能性もあります。
本人と連絡が取れずシフトが入れられない
パート・アルバイトと連絡が取れなくなったり、シフト希望を出さなかったりした場合も、会社は対応に困ることがあります。
労働日が契約で決まっている場合
会社は契約に基づきシフトを組めばよく、出勤しなければ「正当な理由のない欠勤」となり、懲戒処分や契約解消事由となり得ます。
労働日がシフトで決まる場合
会社は、本人に希望がないとして労働日「0」のシフトを組むことも考えられますが、この場合、欠勤扱いにはなりません。
一方で、会社の判断でシフトを組み、それを通知することで労働日を確定させ、出勤しない場合は正当な理由のない欠勤として処理する方法も考えられます。
裁判所はどう考える?参考となる事例を紹介
裁判所は、シフト制における雇用契約の内容をめぐる紛争について、いくつかの観点から判断を下しています。
採用時のやり取りから契約内容の合意を認定
医療法人社団新拓会事件(東京地判令和3年12月21日)では、職員が「シフト表どおりに勤務する義務はない」と主張したのに対し、裁判所は「就業規則に基づき、勤務シフトは労使合意により決定されるもので、労働者はその勤務日に就労義務を負う」と判断しました。
採用時のメッセージのやり取りから、【固定した労働日および労働時間とする合意が成立していた】と認定された例です。
勤務実態等から契約当事者の意思を合理的に解釈して認定
ホームケア事件(横浜地判(控訴審)令和2年3月26日)では、雇用契約書に週5日程度と記載されつつも、業務状況に応じて日数を決める旨が記載されていたため、裁判所は、勤務実態や証人尋問の結果を踏まえ、契約当事者の意思を合理的に解釈し、【週4日が所定労働日数であった】と判断しました。
萬作事件(東京高判平成30年1月25日)でも、継続的な勤務形態から最低週4日の勤務が確保されるという「黙示の合意」を認定し、不足分の賃金支払いを会社に命じています。
大幅削減はシフト決定権限の濫用に当たり違法
シルバーハート事件(東京地判令和2年11月25日)では、雇用契約書に勤務日数の記載がなく「シフトによる」と定められていた事案で、裁判所は労働者の不利益が著しいことから、【合理的な理由なくシフトを大幅に削減した場合は、シフト決定権限の濫用に当たり違法となり得る】と判断しました。
これらの裁判例からわかるように、雇用契約書に明示がない場合でも、採用時のやり取りや実際の勤務実態、さらにはシフト決定権の行使が適切であったかが、トラブル解決の大きなポイントとなります。
会社がすべき【実務的な】対応マニュアル6選
企業がシフト制を適切に運用し、トラブルを回避するためには、以下の実務的な対応策を検討することが重要です。
①募集・契約締結時の労働条件の明確な明示
労働基準法では、労働契約締結時に労働条件を明示することが義務付けられています。
シフト制労働者においては、特に以下の点に注意が必要です。
•始業および終業の時刻について
「単に『シフトによる』と記載するだけでは足りず、労働日ごとの始業および終業時刻を明記するか、原則的な時刻を記載した上で一定期間分のシフト表を交付するなどの対応が必要です。
•休日について
休日が確定している場合はそれを明示し、確定していない場合は休日の設定に関する基本的な考え方を明示しなければなりません。労働基準法に基づき、毎週少なくとも1回または4週間を通じて4日以上の休日を与えることを明確にする必要があります。
•募集段階での明示
求人票等の記載時点においても、労働条件は可能な限り具体的かつ詳細に明示するよう配慮が必要です。
②就業規則の整備
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成・届出義務があります。シフト制労働者についても、以下の点を整備しましょう。
•「個別の労働契約による」や「シフトによる」という記載だけでなく、基本となる始業および終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」旨や「具体的にはシフトによる」旨を規定します。
•変形労働時間制を導入する場合は、就業規則において具体的な労働日や各日の始業・終業時刻のパターン、シフト表の作成手続き、周知方法などを定めておく必要があります。
③シフト作成・変更ルールの明確化
会社が一方的にシフトを決めることは望ましくありません。労働者との話し合いを通じて、以下のルールを定めておくことが適当です。
【作成】に関するルール
・シフト表作成にあたり、事前に労働者の意見を聴取すること。
・確定したシフト表の労働者への通知期限や方法。
【変更】に関するルール
・確定したシフトの変更は労使双方の合意が必要です。
・変更を円滑に行うため、変更の申し出期限や手続きを定めておくことが考えられます。
このようなルールを定めることは、労働者にとっては予測可能性を高めるメリットがあり、会社にとってもシフト決定の判断に合理的な理由があるという評価材料になります。
④労働日・労働時間などの設定に関する基本的な考え方の合意
労働契約の内容に関する理解を深めるために、シフト制の基本的な考え方をあらかじめ労働契約で取り決めておくことが望まれます。例えば、労働者の希望に応じて以下のような内容を話し合って合意することが考えられます。
• 一定期間において、労働する可能性がある最大の日数、時間数、時間帯
(例:「毎週月、水、金曜日から勤務する日をシフトで指定する」など)。
• 一定期間において、目安となる労働日数、労働時間数
(例:「1か月〇日程度勤務」、「1週間当たり平均〇時間勤務」など)。
• 一定期間において、最低限労働する日数、時間数
(例:「1か月〇日以上勤務」、「少なくとも毎週月曜日はシフトに入る」など)。
これらの合意内容は、できる限り書面により確認しておくことが望ましいです。
⑤適切な労務管理の実施
シフト制労働者であっても、労働基準法をはじめとする労働関係法令は他の労働者と同様に適用されます。
•労働時間管理
1日8時間以内、1週40時間以内の法定労働時間を遵守し、時間外労働や休日労働には36協定の締結・届出が必要です。シフト制では所定労働時間が一定でないため、日ごとの労働時間管理を適切に行うことがより重要です。
•休憩時間・年次有給休暇
労働基準法に基づき、適切な休憩時間を与え、年次有給休暇の取得を認める必要があります。休業手当も、会社側の責任による休業の場合には支払義務が生じます。
•その他
安全衛生教育や健康診断の実施、解雇・雇止めの際の規定遵守など、関係法令を遵守し安易な労務管理とならないよう注意が必要です。
⑥連絡が取れない・シフト希望を出さない場合の対応
労働日数や労働日が契約で決まっていない場合、シフトを確定させないと労働日が確定しません。
正当な理由なく就労を拒否している事案の場合には、会社側がシフトを組み労働日であることを確定させておくことも検討すべきです。
その上で欠勤すれば、正当な理由のない欠勤と評価できます。
出勤の意思を示さない場合や、容認できない理由ですべての日を休日希望として提出された場合(例:「しばらく働きたくないので6カ月間、休日希望でお願いします」など)には、
•シフト自体は決定し労働日を確定すること
•実際に来るならば前日までに連絡すること
•出社しない場合は正当な理由のない欠勤として扱うこと
などを明記した通知書を出すことも検討しましょう。
結論|シフト制は設計と運用がすべて
シフト制は、企業が業務を柔軟に調整し、労働者が自身のライフスタイルに合わせた働き方を実現できるという点で、現代において非常に有効な雇用形態です。
しかし、その柔軟性ゆえに、労働条件の曖昧さから生じる労使間の認識のずれが、シフト削減や労働時間、賃金に関するトラブルに発展するリスクをはらんでいます。
こうしたトラブルを未然に防ぎ、健全な労務管理を推進するためには、労働契約の締結時における労働条件(労働日、労働時間、始業・終業時刻、休日など)の明確な明示が不可欠です。
また、就業規則の適切な整備、シフト作成・変更に関する明確なルール作り、そして労働日・労働時間設定に関する基本的な考え方の事前合意も極めて重要となります。
万が一、労働者との間で認識のずれが生じた場合でも、採用時のやり取りや実際の勤務実態、そして会社がシフト決定権を適切に行使していたかが、裁判所での判断材料となることを理解しておく必要があります。
労務のプロ、社労士に依頼するメリット
•法令適合の“型”を最短で整備
雇用契約書・就業規則・シフト運用マニュアル(作成/変更/通知)まで一気通貫で整えるため、抜け漏れや表現の不備によるトラブルを未然に防ぎます。
•紛争予防の“証拠化”を設計
募集時の明示、合意取得、シフト通知・変更の記録(電磁的記録を含む)を標準化し、万一の監督署対応・訴訟でも説明可能な状態にします。
•実務で回る運用フロー
シフト希望の回収→作成→確定→共有まで、現場が迷わない手順をご提案します。
•人件費と法令の両立
変形労働時間制・36協定・有給付与管理といった“数字の設計”を支援し、コスト最適化とコンプライアンスの両立を図ります。
•監督署・是正対応に強い
指摘が入りやすい論点(明示不足/変更記録の欠落/休憩・割増の扱い等)を踏まえ、点検→改善→再発防止まで伴走します。
アーチスでは、ひな形の提供だけで終わらない“運用設計”を重視しています。
御社の業態・客数の波・スタッフ構成に合わせて、現場で回る仕組みを一緒に作ります。
お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。
こんな記事も読まれています
プロフィール

神奈川県平塚市
社会保険労務士法人・行政書士法人
アーチス
労務に関わる手続き・問題から助成金まで、幅広くお問い合わせに対応していますのでどうぞ安心してご相談ください。
関東エリアを中心に遠方のお客様はZOOMミーティングにより全国どこからでもリモートでのご対応が可能。
20人以上の専門性を持ったスタッフが対応を手厚く、よりスピーディーに行います。